
我が家には、年長、年少の2人の子どもがおります。
年長の息子はいよいよあと半年で小学生になります。息子は来年度へ向けて就学前検診に参加したり、私も近隣の小学校へ公開授業を見学に行ったりと、親子ともに来年度の小学校入学を意識するようになってきました。
楽しみなこともあれば、少し不安なこともあります。
先日の座談会では、私のそんな複雑な気持ちをちえみさんにお話しました。
現役世代のコミュニティ内にいると、盛り上がっている早期知育の流れに引っ張られますが、それとは一線を画す、子育てが終わったちえみさんだからこその視点でのご意見を伺いました。とても参考になりましたので、ブログでもご紹介したいと思います♪
Contents
小学校の英語授業を見て感じたこと
冒頭でも書きましたが、先日、小学校の外国語(英語)の授業を見学する機会がありました。
そこでは、2年生がALT (Assistant Language Teacher)のネイティブの先生の授業を受けていました。息子が進学する予定の小学校では、英語の授業は3年生からという話を耳にしていましたので、より低学年から開始していることにやや驚きました。ですが、授業の内容自体は、ALTの先生が中心となり、子どもがゲーム感覚で積極的に声を出していくようなもので、私としては好印象でした。
一方、6年生の英語の授業は私が想像していたよりも進んだ内容でした。書き取りこそなく、アクティブラーニング形式ではあるものの、ゆとり世代のスプが中学校1年生の1-2学期に習っていたようなレベルの文法や構文は知っている、また理解できていることが前提のような高度な授業内容でした。ついていけるお子さんは積極的に発言していましたが、すでにクラス内ではっきりとした英語力の差が生じていることは、少し見学をしただけのスプにも一目瞭然でした。
中学英語の二極化が顕在化しているそうですが、実際に小学校の授業を見学したことで、この授業内容が既習のものとして中学校が始まるのであれば、最初のペーパーテストで二極化してしまうのは当然だと実感いたしました。
また、私が想定していたよりも早い年齢から、日本語を介して英語を教えている現状を目の当たりにし、率直に言って、私のおうち英語の方針とは違うと感じてしまったのです。小学校の授業が進む前に、自宅で母国語方式のおうち英語に時間をかけておく必要があると感じました。
学校教育の本当の価値とは
学校に対する考え方
このような私の感想、やや不安になってしまった気持ちを「おうち英語の会」の座談会でお話したところ、このブログの管理人であり「おうち英語の会」の主宰者であるちえみさんからは、次のようなお話がありました。
学校英語は気にしすぎない

そもそも、学校の英語で何を教えられても、よいではないですか?
授業で点数が取れる、取れないはもちろんあると思います。ですがそれはあまり気にせず、今まで通り楽しくおうち英語を続けて、必要なインプットをして、「英語が本当に出来る」ようにしておけば、どんな授業であってもいいと思いますよ🐵
学校教育の捉え方を変えてみる

授業が「なんだか変」「物足りない」と子どもが感じるかもしれませんが、それを友達と「変だったよね~」と笑いあえるような、楽しい時間であることが学校教育の一番の価値なのではないでしょうか。
学びを得ることより、楽しい時間を過ごすことこそが、学校教育には価値があるのです。そう捉えると、子どもが楽しそうだから良い、ときっと思えますよ。
現実的な対応策
- 学校でやっていることで足りないと思うのであれば、それは英語に限らず、課外活動や習い事で補うのが現実
- 多少授業の進度ややり方に気になることがあっても、本当に必要なことを、家でしっかり親が見ていれば大丈夫
引っ越しが多いちえみさんの経験から

ですので、学校に多くを求めたことはなく、むしろ求め過ぎなければとてもありがたい場所であると思いますよ。
子育てで大切なこと
ちえみさんからは、こんなお話もありました。
- 学力より、どんな時でも前向きに立ち上がれる子に育つことが一番大事。
- この子ならなんとかなるはず、と、信頼できる気力/体力のある子に育てておく。
- 学校で余計なことを教えられる前に、英語回路を作っておかねば…!とか、心配しすぎない。
- とにかく、学校教育に多くを求めすぎない!心配しすぎない!
このお話を聞き、スプが「前向きな気持ち、強い気持ちを育てることは、勉強を教えるより難しいのではと感じている」とお伝えしたところ、

一番は、とにかく分かりやすく愛情を伝えることではないでしょうか。
私は七田式の教室で、毎日欠かさず8秒間ぎゅっと抱きしめ、大好きだよと伝える、ということを教わり実践してきました。
メンタリティのサポートに関しては様々な方法論があるでしょうけれど、一番の肝は、親はあなたを無条件で大切に思っている、と、本人が分かる形で伝え続けることでは?
そうやって親に信じてもらって育つと、成長して逆境の中でも自分を信じられる子に育つと思いますよ。
まとめ
ちえみさんのご回答、いかがでしたか?
小学校の英語教育への親の向き合い方のポイントは
- 学校が全ての面で個別最適化した教育をしてくれる、という期待をしすぎない
- 物足りないと感じたら、自宅や習い事で補強していくのが現実的
- 本当の英語力を身に着けるために必要なインプットをおうち英語で十分にしていれば、学校でどんな風に教わっても大丈夫
ということでしたね。
お子さんが成人され子育てがひと段落されたちえみさん。その俯瞰した視点からお話を伺うと、日頃は目先の事にとられていて、子育ての中で一番大切なことを忘れがちに過ごしていることに気づくことが出来ます。
同世代ママさんと話していると、どうしても目の前の困りごとに気持ちが集中してしまいます。もちろんその困りごとを具体的に解決することは重要なのですが、ちえみさんとお話をしまして、私は無意識のうちに、小学校に学習面のことをすっかりお任せするような気持ちでいたのだと気が付きました。
小学校は自分の子どもに合わせて授業を展開してくれる場所ではない、ということは理解しておくべきですね。
これからの学校教育の変化は予測できませんが、教育環境が大きく変わっていくのは理解した上で、全てを学校に任せきりにするのではなく、必要なことは親もしっかりと教えていくべきですし、最後は子ども自身で勉強するものですよね。
更に、何よりも大切なのは、子どもが楽しく学校生活を送ることですね。
最後の「子育てで大切なこと」の部分でお話いただいたことは、子どもの自己肯定感、自己効力感を伸ばすために本当に大切な考え方だと思います。繰り返しになりますが、つい目先の不安に心が囚われてしまいますが、子どもが幸せか、楽しんでいるか、そんな視点を忘れずに子育てをしていきたいものです。
ちえみさん、いつも貴重なお話をありがとうございます✨

インスタグラムでは会員さんのリアルな取り組みの様子が日々投稿されていますので、ぜひチェックしてみてください♪
「おうち英語で子供をバイリンガルに育てたいけど、一人でできるかどうか不安」というお母さん(お父さん)のために「おうち英語の会」をやっています。興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。


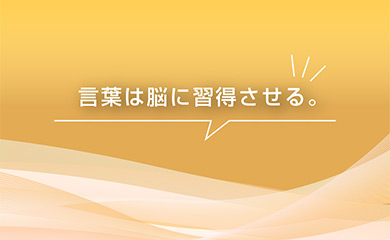
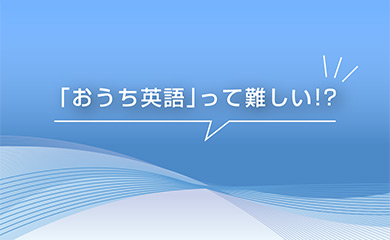



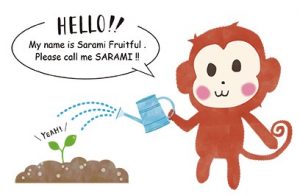
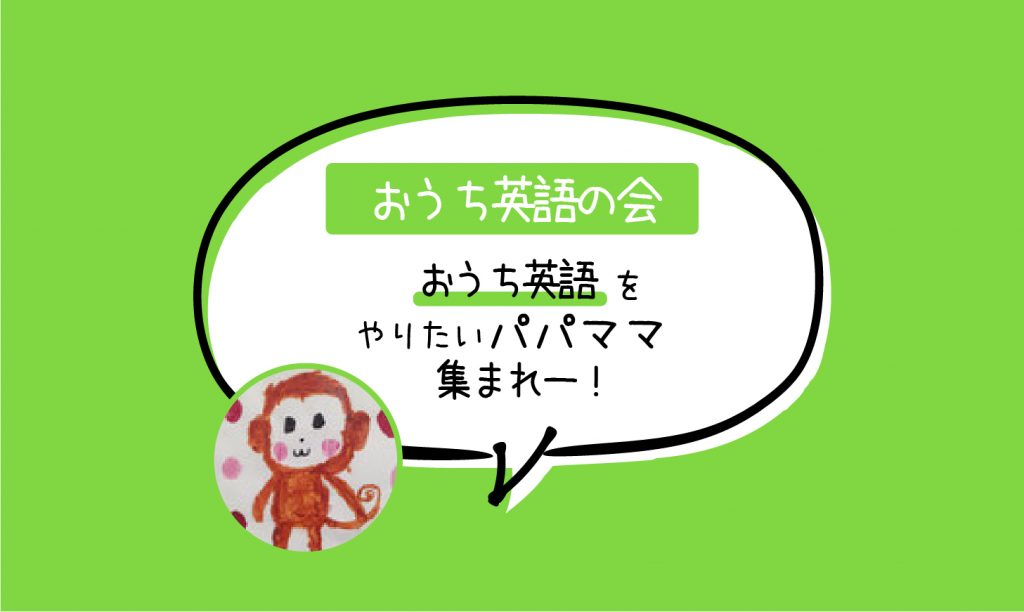
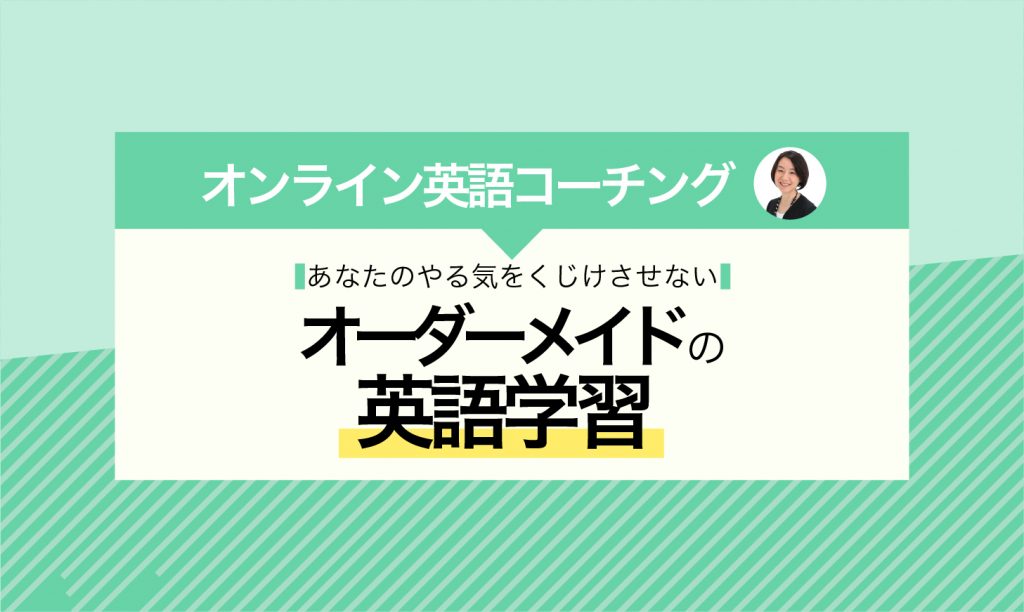

「おうち英語の会」会員、ブログ担当のスプです。